

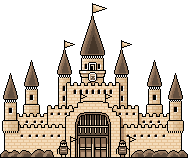
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
<小便小僧> 山手線外回り・京浜東北線南行ホームの田町寄りに設置されてる。 季節によって衣装を変えることで知られ、 通勤・通学客の目を楽しませている。 1952年(昭和27年)、10月14日の鉄道開通80周年に際して、 当時の浜松町駅長の椎野栄三郎が、 何か記念になるものはないかと新橋駅の嘱託歯科医だった友人の小林光に相談し、 小林の長男誕生記念に作られて診療所の庭に置かれていた 白い陶器製の小便小僧が寄贈されたのが最初。 当初は衣装はなく、裸の状態であった。 ある寒い日に女の子が毛糸の帽子を被せたのが衣装を着せた。 その後、浜松町の会社に勤務していた 田中栄子という女性が衣装を作成して着せるようになった。 1986年(昭和61年)には、東京消防庁芝消防署から防災PR用に 小便小僧に着せる消防服を作って欲しいと 港区の手芸グループ「あじさい」に依頼があった。 それをきっかけとして同年11月から再び着せ替えが始まり、 それ以降は「あじさい」により衣装が毎月変更されている。 ※久しぶりにリフレッシュできました! |
|
 小便小僧(1月) |
世界的に有名な 『小便小僧:ジュリアン君』は 大変な衣装持ちですが、 浜松町の『小便小僧』も 季節によって衣装を変えているそうです。 |
 小便小僧(6月) |
世界的に有名な 『小便小僧:ジュリアン君』は 大変な衣装持ちですが、 浜松町の『小便小僧』も 季節によって衣装を変えているそうです。 |
 小便小僧(12月) |
世界的に有名な 『小便小僧:ジュリアン君』は 大変な衣装持ちですが、 浜松町の『小便小僧』も 季節によって衣装を変えているそうです。 |
 小便小僧のモザイクレリーフ |
2009年の開業100周年記念で、 改札外コンコースに 小便小僧のモザイクレリーフが設置された。 |